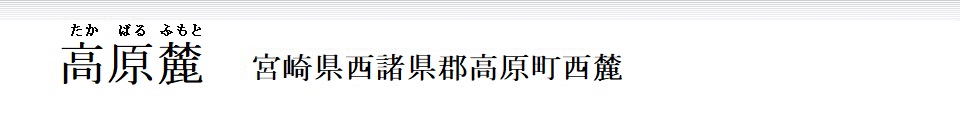鹿児島県と宮崎県に残る旧薩摩藩領内の外城と麓の町並み記録です。
高原(たかばる)町は,霧島連山の東麓に位置し,背後に名峰・高千穂峰がそびえ,天孫降臨の伝承が残る町です。藩政時代の高原郷は島津氏の直轄領で,地頭仮屋は麓村に置かれ,鹿児島から地頭が派遣されました。高原麓は小さな麓ですが,往時の麓の遺構が今も残っています。

高原麓の武家門
左右に小屋根を備える立派な門。扉は観音扉のようであり,潜り戸のようなものも見えます。
 高原麓の町並み(左)
高原麓の町並み(左)
中世の高原(たかばる)は,税所氏,北原氏,日向の伊東氏,島津氏の勢力争いの場となり,天正4年(1576),伊東氏の守る高原城を島津氏が攻め落としたことにより,島津領(直轄領)となり,以後明治に入るまで高原は島津氏の支配下に置かれました。
江戸時代の高原は,薩摩藩外城の一つとなり,地頭仮屋は現在の遍照寺付近にあったと言われます。地頭はもっぱら島津氏の家臣が任命され,高原に常駐することはなく,普段の政務はあつかい役(後の郷士年寄)が行っていました。また、薩摩・大隅・日向から多くの郷士が高原に移住したようです。

高原麓の町並み(西麓下麓)
切石積みの石垣と武家門が見られます(上下)。

高原麓の町並み(西麓下麓)
 高原麓に残る屋敷林(左)
高原麓に残る屋敷林(左)
高原は,背後に高千穂峰がそびえて古くから天孫降臨の土地として認識されており,薩摩藩の「三国名勝図會」に「高原は高天原の略称と伝わる」と書かれています。
高千穂峰(霧島山)は有史以来噴火が相次ぎ,度々被害をもたらす一方で,山岳信仰の対象となり,中世末期から近世にかけて,「霧島六所権現」と呼ばれる6つの寺社が整備されました。
高原には「狭野神社」「霧島東神社」の2社が建っています。

高原麓の町並み(2010年)
左の大木は高さ23メートルもあるモミの木。上の屋敷はモミの木を残し更地となり,現在(2025年)はコンビニの駐車場となっています。

高原麓の石柱門(西麓下麓)
遍照寺付近。

高原麓の町並み(西麓下麓)
左右に生垣と石垣が続く小道が残る。
 高原小学校(西麓上麓)
高原小学校(西麓上麓)
高原小学校は明治2年の郷学校を起源とし,2024年に創立150周年を迎えた。明治4年に旧地頭仮屋跡から現在地に移転。

高原小学校旧講堂(西麓上麓)
昭和11年に建設された木造建築物。側面に控え壁を備え,柱形を見せ,赤い屋根にピンクや白で彩られた洋風外観が特徴。現在は高原町民体育館分館として利用されています。国の登録有形文化財。
訪 問:2010年5月4日
備 考:狭野神社,霧島東神社,狭野神楽,祓川神楽。天孫降臨の舞台は同じ宮崎県の高千穂町が有名ですが,高千穂峰も天孫降臨の有力地として知られます。
参 考:高原町の文化財,高原所系図,高原町ホームページ等
| 戻る|
|ホーム|
戻る|
|ホーム|

高原麓の武家門
左右に小屋根を備える立派な門。扉は観音扉のようであり,潜り戸のようなものも見えます。
 高原麓の町並み(左)
高原麓の町並み(左)中世の高原(たかばる)は,税所氏,北原氏,日向の伊東氏,島津氏の勢力争いの場となり,天正4年(1576),伊東氏の守る高原城を島津氏が攻め落としたことにより,島津領(直轄領)となり,以後明治に入るまで高原は島津氏の支配下に置かれました。
江戸時代の高原は,薩摩藩外城の一つとなり,地頭仮屋は現在の遍照寺付近にあったと言われます。地頭はもっぱら島津氏の家臣が任命され,高原に常駐することはなく,普段の政務はあつかい役(後の郷士年寄)が行っていました。また、薩摩・大隅・日向から多くの郷士が高原に移住したようです。

高原麓の町並み(西麓下麓)
切石積みの石垣と武家門が見られます(上下)。

高原麓の町並み(西麓下麓)
 高原麓に残る屋敷林(左)
高原麓に残る屋敷林(左)高原は,背後に高千穂峰がそびえて古くから天孫降臨の土地として認識されており,薩摩藩の「三国名勝図會」に「高原は高天原の略称と伝わる」と書かれています。
高千穂峰(霧島山)は有史以来噴火が相次ぎ,度々被害をもたらす一方で,山岳信仰の対象となり,中世末期から近世にかけて,「霧島六所権現」と呼ばれる6つの寺社が整備されました。
高原には「狭野神社」「霧島東神社」の2社が建っています。

高原麓の町並み(2010年)
左の大木は高さ23メートルもあるモミの木。上の屋敷はモミの木を残し更地となり,現在(2025年)はコンビニの駐車場となっています。

高原麓の石柱門(西麓下麓)
遍照寺付近。

高原麓の町並み(西麓下麓)
左右に生垣と石垣が続く小道が残る。
 高原小学校(西麓上麓)
高原小学校(西麓上麓)高原小学校は明治2年の郷学校を起源とし,2024年に創立150周年を迎えた。明治4年に旧地頭仮屋跡から現在地に移転。

高原小学校旧講堂(西麓上麓)
昭和11年に建設された木造建築物。側面に控え壁を備え,柱形を見せ,赤い屋根にピンクや白で彩られた洋風外観が特徴。現在は高原町民体育館分館として利用されています。国の登録有形文化財。
訪 問:2010年5月4日
備 考:狭野神社,霧島東神社,狭野神楽,祓川神楽。天孫降臨の舞台は同じ宮崎県の高千穂町が有名ですが,高千穂峰も天孫降臨の有力地として知られます。
参 考:高原町の文化財,高原所系図,高原町ホームページ等
|
Copyright (C) Tojoh Archives. All Rights Reserved.